 |
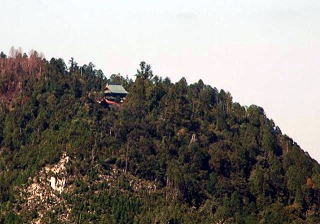 |
| 福王寺高堂 | 福王寺山山頂 |
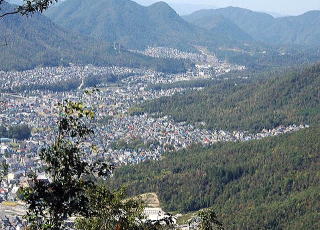 |
 |
| 福王寺西側(大毛寺付近) | 福王寺東側(南原・綾ケ谷) |
 |
 |
| さざれ石 毛利元就が豊臣秀吉に贈る | 不動明の悪夢に耐えきれづこの地に帰る |
 |
 |
| 銀山城主武田伊豆守氏信公供養塔 | 金の甲羅を持つ亀の住む金亀池 |
福王寺と武田氏
 |
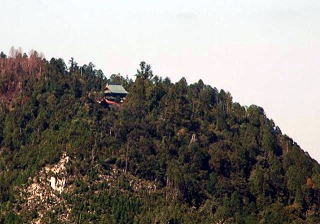 |
| 福王寺高堂 | 福王寺山山頂 |
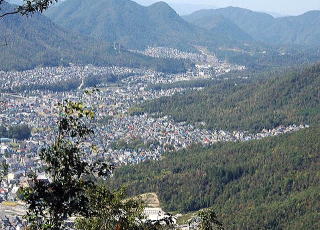 |
 |
| 福王寺西側(大毛寺付近) | 福王寺東側(南原・綾ケ谷) |
 |
 |
| さざれ石 毛利元就が豊臣秀吉に贈る | 不動明の悪夢に耐えきれづこの地に帰る |
 |
 |
| 銀山城主武田伊豆守氏信公供養塔 | 金の甲羅を持つ亀の住む金亀池 |
弘法太子開基と伝えられる福王寺も、いつの頃から哀微しかわって正和四年(1315年)河内の人である禅智上人が往来し、中興をはかった。この企てを援助したのが武田氏で、高堂を再建し、本尊に両脇士を添えたほか大師影堂、熊野権現十二所、求聞持堂、厳島神社、諸天堂、仁王門を寺領に寄進した。後醍醐天皇は、このことを禅智から聞き大勝金剛院の号を授け、また僧良海の時には「郡中寺社悉(ことごとく)くを以って門主となす」となっています。
応永六年良海は勅を奉じて東寺の仏舎利と大師の真影を受け、これを奥の院に安置した。福王寺の中興はこうした事情と、武家勢力の抬頭とくに武田氏の権限の深化、可部方面への進出を背景として行はれたものであります。
武田氏は福王寺への所領の寄進と安堵を相次いで行なった。、武田氏のこのような福王寺外護者としての役割は同時に僧の任免、寺規の制定への関与を伴うようになっていった。長緑四年(1460年)には「禁制福王寺領山上山下条々」は大膳太夫源朝臣の名において出されています。その内容は 一、山木を伐採すること ・ 一、女人夜宿のこと ・一、来往の僧侶並びに乞食入るべからざること ・ 一、軍勢甲乙人等寺領に進入べからざること ・ 一、寺領において殺生すべかざること。
長緑四年の「福王寺々僧官位事」によれば権少僧都5人、権律師10人、阿闍梨10人とその定員を25人としていることからもこの寺の規模を覗うことができます。
武田氏が没落し、可部の豪族中山備後氏が熊谷に滅ぼされた跡は、福王寺の一帯は熊谷氏の本領に繰り込まれ、天正二年(1574年)熊谷直信が登山し尊像を拝した時、霊亀が池面に浮かび長さ5尺余の金色の甲羅、赤い喉をみせるという奇端が現れたという伝承が伝えられています。また同時に「さざれ石」と言う奇岩があり、豊臣秀吉がこの名石の噂を聞き毛利輝元に輸送させ庭に据えたが、夢中に不動明が切りかかる胸騒ぎを覚えることが再三に及んだことで寺に返すと共に金子100両を寄附したと言う伝承もあります。
同寺は少なくとも、江戸始めの宗門改めまでは郡内真言寺院の総元締めとしておもきをなし、近郊では、宮島の大聖院、廿日市の極楽寺、志和の並滝寺と並び修業僧の寺として繁栄したものの、今では門徒も極めて少なく、葬儀を行わない点にこの寺の性格をとどめています。