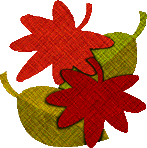 安芸之国 三滝観音寺
安芸之国 三滝観音寺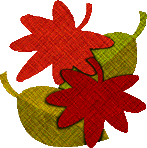 安芸之国 三滝観音寺
安芸之国 三滝観音寺
![]()
三滝寺縁起
七つの川の流れる広島の北西の川に沿って聳える三滝山の谷間に位置する三滝寺は、三滝の観音さまとして親しまれている真言宗高野山派の古刹です。
その開祖は、真言宗の開祖弘法大師空海が809年(大同4年)、唐への留学を終えての岐路、当山に巡錫され、末世有縁の霊地なりと、聖観世音菩薩の梵字を自然石に刻まれ、滝の飛沫のかかる岩窟に安置されたことに始まると伝えられている。
爾来千百有余年、芸州銀山城主武田氏や、安芸藩主浅野公の信仰と庇護を受けると共に、一方では江戸時代に民衆に口ずさまれた「広島八景心願成就」のなかで「心はさきだつははのため・・・・・みたき観音札おさめ・・・・」と詠われたように、広く人々の信仰を集めてきた。
境内には水量の異なる三つの流れが瀬音を響かせ、各水流が滝を有していることから三滝寺と呼ばれているが、明治時代には龍泉寺とも称していた。又旧藩主浅野公をはじめ、信徒の植えた楓樹が鬱蒼と繁り、緑陰の岩巌は苔むして深山幽谷の趣が深く、広島市民の憩いの地となっています。
![]()
 |
 |
| 石仏・地蔵尊の続く参道 | 延命地蔵「呆け払い」観音 |
 |
 |
| 鎮守堂 | 本堂 |
 |
 |
| 梵鐘 | 本房 |
 |
 |
| 多宝塔 | 茶屋 |
 |
 |
| 茶房 「空点庵」 | 六角堂 |
本堂
観音本堂の建立年代は不明であるが、銀山城主武田刑部大輔源信守(鎌倉時代)が本堂を修築したことが記録され、その後明治初年明禅僧正によって方形瓦葺のお堂に改築されたが、大正年間の再々にわたる水害と昭和の原爆によって半壊した。
昭和43年再建に着手、平安時代の建築様式の粋を集めた簡素で優美、すっきりとした線を生かした構造の美しさをよく現した姿が、岩を咬むように建っている。檜造りの寄棟瓦葺浅野博士の設計による。
鎮守堂・鐘楼
鎮守堂は、四鬼神和尚が当山の安寧のため山上に勧請祭祀されたもので、四鬼神和尚は法力に優れた人で「三滝の天狗」と呼ばれ、当山の信仰の基礎を築いた人である。
鐘楼は、「爺さん起きなよ三滝の鐘じゃ、なすも、かぼちゃも眼を醒ます」と詠われ参拝の人々がつく鐘の音が谷間に響き渡ります。
多宝塔 県重要文化財
多宝塔は、三滝寺信徒達が原爆及び第二次世界大戦死没者の冥福と、平和開顕を祈って建立を発意し、紀州の広八幡神社より遷座、昭和26年5月に落慶した。
塔の創建は「大永六年(1526年)法界衆生の為,之を建つ」と記されている事から、室町時代の建立と分るが様式的にも室町時代の特徴を好く表していて、繊細優美女性的な印象を与える姿である。構造も、和様唐様折衷で、丁寧なつくりとなっています。但し江戸時代津波によって倒壊し、再建されている為多少の変更が加えられています。